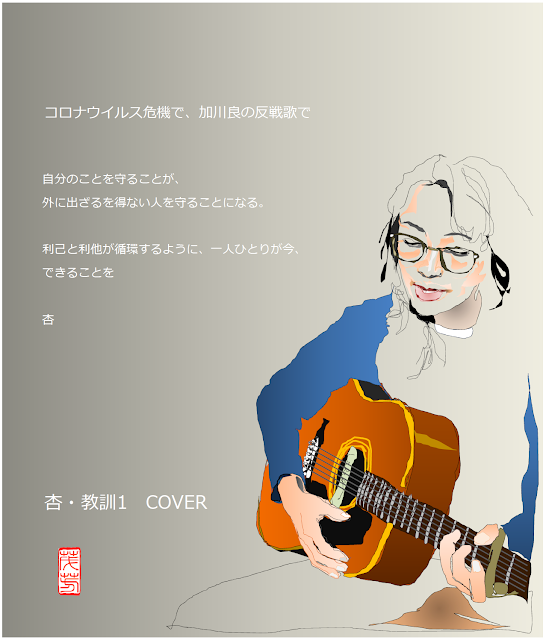私が気に入った新聞コラム
CO2は生命育む恵みの物質
東京大学名誉教授・渡辺正氏
約30万種の陸上植物は、太陽光を動力にした光合成で、安定な水とCO2から高エネルギー物質を作る。
大気に増えるCO2は、むろん地球の緑化を進め、ひいては私たちの食糧を増やしてくれる。
まったくその通りですね。
日本のマスコミはなぜ科学的に正しいことを報道しないのか?
大変勉強になったコラムです。
 |
| 東京大学名誉教授・渡辺正氏 |
渡辺 正(わたなべ・ただし)は東京理科大学教授。1948年鳥取県生まれ。東京大学大学院修了、工学博士。東京大学助手、助教授を経て1992年より同大学教授(生産技術研究所)。2012年、同大学を定年退職(名誉教授)ののち東京理科大学に勤務。専門は生体機能化学、科学教育、環境科学。
CO2は生命育む恵みの物質
東京大学名誉教授・渡辺正
CO2を悪とみる1988年以来の発想は、中世の魔女狩りに似て、社会を壊すエセ科学だった。かつて35年ほど光合成を研究した工学系の化学屋が、そう断じる根拠をご披露したい。
快適な暮らしもその恵み
約30万種の陸上植物は、太陽光を動力にした光合成で、安定な水とCO2から高エネルギー物質を作る。必須物質の全部を生合成する植物は、単独で繁栄できる。
物質合成能の低い動物は、植物の「製品」を強奪して生きるしかない。草食動物はむろんのこと、肉食動物も間接的に植物を食べている。要するに植物から見た動物は「寄生虫」にすぎない。
大魚や鯨を頂点とする海中の食物連鎖も、植物プランクトンと藻類がCO2から作る有機物を原点にして成り立つ。
私たちも植物の恵みで生きる。飲食物のうち、水と食塩を除くほぼ全部が、直接間接の光合成産物だとわかる。体重72キロの筆者を作る13キロの炭素原子も、元は大気中のCO2分子だった。
光合成は、私たちに飲食物のほか材料(木材など)と繊維(綿・麻・紙)も恵む。1億~2億年前の光合成産物は、化学変化して石油や石炭、天然ガスになった。
文明や文化を創造し、快適な暮らしと移動法を手に入れ、情報化社会を作ったヒトも、食物から産業用動力までの全部を植物に頼る。高層ビルが演出する都会の華麗な夜景も植物の恵み、つまりはCO2の恵みだと心得よう。
CO2増え豊かさ増す世界
CO2削減の声が芽生えてから大合唱に育つまで35年余、大気のCO2濃度は増え続けた(たまたま同時進行した昇温の原因は多様)。直近の25年間はペースを上げながら15%以上も増え、世界を豊かにしつつある。なぜか?
大気に適量の酸素がたまった4億~5億年前に緑藻の一種が上陸し、分化・進化を経て1億~2億年前の恐竜時代に大繁栄した。葉の化石を調べた結果などから、当時のCO2は現在の5~10倍も濃かったと推定されている。
当時の生物を先祖とする植物に、今のCO2は薄すぎる。だからこそ本格的ハウス栽培では、石油燃焼装置を使って内部のCO2濃度を外気の3~4倍に上げ、植物=作物の生育を速める。
大気に増えるCO2は、むろん地球の緑化を進め、ひいては私たちの食糧を増やしてくれる。
衛星観測によると地球の緑は、30年間に約10%ずつ増えてきた。作物の収量も快調に増えた状況を、国連食糧農業機関(FAO)の統計が語り尽くす。食糧の増加は、8億人以上ともいう飢餓人口の低減にも貢献してきた。
そんなCO2を減らすのは、全人類に向けた大犯罪だろう。
カネと利権「CO2悪玉論」
CO2は、気温変動の主因ではない。たとえばCO2が単調に増え続けた過去2千年のうち、10~13世紀は今よりだいぶ暖かく(中世温暖期)、江戸期を含む14~19世紀は寒かった(小氷期)。
先述の1億~2億年前は、気温も3度は高かったとおぼしい。それでも熱暴走など起きず、生物が栄えたわけだから今後、CO2が倍増しても問題はない(CO2の赤外線吸収は飽和に近いため、倍増時でも昇温は0・5度未満)。
だが国連は、東西冷戦の終結が見えた88年、CO2温暖化危機を口実に、排出の多い先進国の富を途上国へ流す南北調停仕事を思いつく。だから定例集会COPでも、近年は「カネよこせ(途上国)」と「ちょっと待て(先進国)」の口論だけをやってきた。
実のところ国連の企(たくら)みは、とうの昔に破綻している。80年代末は途上国だった中国が今や世界一のCO2排出国なのに、国の分類を変えないというルール上、今もって「途上国」なのだから。
けれど、環境浄化が進んで失業に怯(おび)えつつ国連と協働した面々が、一件を「解決可能な環境問題」という虚構に仕立て上げた。
深刻そうな話にメディアが飛びつき、政治家は票を期待して血税を垂れ流す。巨費の利権を産学界の亡者(一部は知人)が狙い、脱炭素など非科学語を操って庶民を騙(だま)す世になった。
政府は昨今、脱炭素・経済成長の営みをエセ英語でグリーントランスフォーメーション(GX)と呼ぶ。10年で投資150兆円を期待するというけれど、「脱炭素」の成功だけはありえない。
たとえば、バイオ燃料のCO2発生量は石油より少ない…と叫ぶ集団がいる。事実なら人類は燃料問題から解放され、化石燃料の大半を掘らずにすむ。だがバイオ燃料はCO2を増やす代物だから、石油採掘が減る気配すらない。
バイオ燃料は善…という噓が、2022年12月の航空法改正(バイオ燃料導入)につながった。審議会に理系の人はいないのか?
なお形容詞「グリーン」は、遠い未来の姿ではなく、CO2が増え、植物界も食卓も豊かさを増す現状にこそふさわしい。
GX関係者はCO2が減ると誤解して喜び、筆者は増えると確信して喜ぶ。私たちは妙な時代を生きている。(わたなべ ただし)